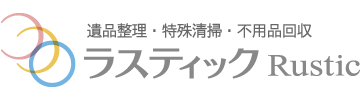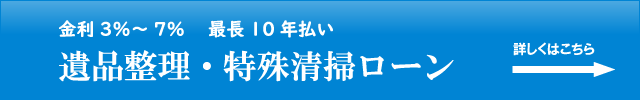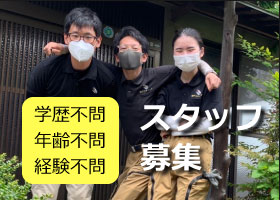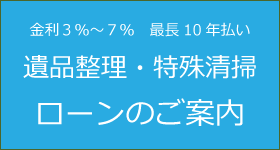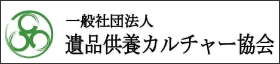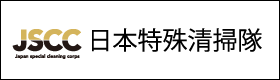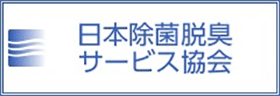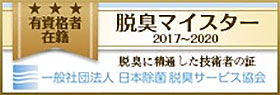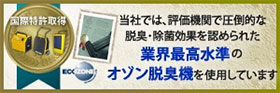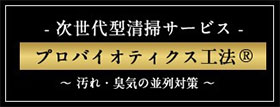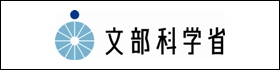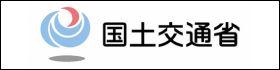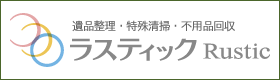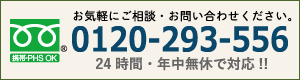2025年8月12日

「片付け」
ゴミ屋敷になる前に
久しぶりに帰った実家。
部屋の隅に積まれた古新聞、
使っていない調理器具、
捨てられずに溜まったビニール袋──
そして
玄関を開けた瞬間にふわっと漂ってくる、
カビ臭のような、生ゴミ臭のような、
独特な「臭い」。
歳を重ねた親にとって、
物を減らすという行為は想像以上に難しく、
気がつけば空気の流れが滞った、
「臭いのこもる部屋」ができあがってしまいます。
このまま放っておけば、
転倒や害虫のリスクだけでなく、
ご近所への臭気トラブルや、
衛生環境の悪化にもつながりかねません。
だからこそ今のうちに始めてほしいのが、
高齢の親と一緒に取り組む “片付け” と “臭い対策”。
大切なのは、
「捨てさせること」でも
「怒って片付けさせること」でもありません。
親の気持ちや思い出に丁寧に寄り添いながら、必要な空間を取り戻すことです。
この記事を読まれているあなた自身の思い出を無くす事も躊躇しているのです。
この記事では
実家がゴミ屋敷になってしまう前に、
臭いと物の片付け、両方に効果的な3つの方法をご紹介します。
親を責めることなく、
暮らしを少しずつ整えていくための一歩に、
ぜひお役立てください。
コンテンツ
なぜ実家はゴミ屋敷になってしまうのか?
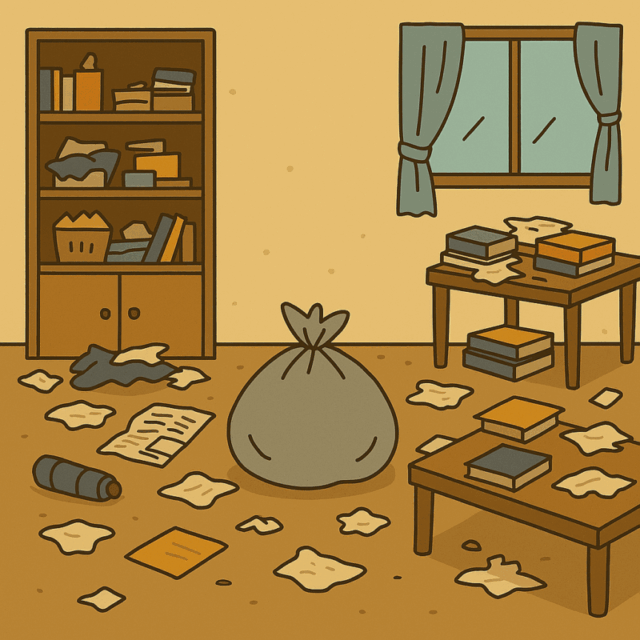
ゆるやかなゴミ屋敷化
気づきにくい「ゆるやかなゴミ屋敷化」
実家が「片付かない」「物が増えている」と感じたとき、
そこには単なる「怠け」ではなく、
いくつかの明確な理由があります。
1. 捨てる判断ができなくなる
高齢になると、
「いつか使うかもしれない」
「もったいない」
という気持ちが強くなります。
戦後を経験した世代ほど、
物を捨てる事に抵抗感を抱いています。
もしかしたら認知症かもしれません。
結果として、
壊れた電化製品や紙袋、空き箱など、
本来不要なはずの物までが、生活空間を圧迫していきます。
2. 体力・視力の衰えで掃除が行き届かない
高い棚の上、
床に落ちた物の拾い上げ、
重たい家具の移動。
これらは加齢による筋力の低下とともに、少しずつ難しくなっていきます。
また、筋力だけでなく視力や嗅覚が低下することで、
ホコリやカビ、臭いに気づきにくくなるケースも珍しくありません。
3. 思い出と生活品の境界が曖昧になる
写真、手紙、趣味の道具など、
本人にとっては「人生の一部」とも言えるものが、部屋のあちこちに置かれています。
客観的には整理や処分の対象であっても、
本人にとっては手放すことが
「過去を否定するようでつらい」
という気持ちが芽生えてしまうのです。
4. 臭いの自覚がないまま蓄積していく
生活の中で染みついてしまった「臭い」は、住んでいる本人ほど気づきにくいもの。
これは加齢とは関係なく誰もが同じだと思います。
とくに以下のような臭いは、
時間をかけて室内に広がっていきます。
- カビや湿気による臭い
- 生ごみや排水口の臭い
- 衣類や寝具に残る体臭
- それらが混ざった生活臭
こうした臭いは、片付けと同時に対処しなければ、
物を減らしても「暮らしやすさ」にはつながりません。
高齢者特有の心理と生活背景
実家が少しずつ物であふれていく背景には、高齢者ならではの心理的・生活的な事情があります。
「ゴミ屋敷にしよう」と思って暮らしているわけではありません。
- 長年の生活習慣
- 年齢とともに変化する心身の状態
- セルフネグレクト
それらがゆっくりと「片付かない家」をつくっていくのです。
物を捨てられない心理
高齢になると
以下のような理由で「物を手放す」ことが難しくなっていきます
- 不 安 : 「いつか使うかもしれない」
- 精 神 : 戦後の物がない時代を経験した世代特有の「もったいない」
- 思い出 : 家族とのつながりや歴史が詰まっている
特に郵便物や紙袋、包装紙、空き箱などをため込んでいるケースは多く、
本人にとっては「整理してある」状態でも、周囲から見ると「ゴミが積まれているように見える」ことがあります。
体力・判断力・視力の低下
加齢とともに、以下のような身体的変化が現れます
- 腰をかがめる動作がつらくなり、掃除が行き届かない
- 掃除機の使用が億劫になり、ほこりが溜まりやすい
- 判断力が低下し、「ゴミかどうか」の区別がつきにくくなる
- 目が悪くなり、部屋の汚れや物の増加に気づかなくなる
さらに
- ゴミの分別ルールの複雑化
- 収集日程の把握
などが難しくなり
「出せないゴミ」が溜まり続けることも少なくありません。
孤立・うつ・認知症の影響
高齢者が社会的に孤立すると、
部屋を整えるモチベーションが低下します。
会話の機会が減り、誰にも見られない空間が徐々に乱れていく──
そのような孤独感が、ゴミ屋敷化を加速させる要因にもなります。
また、うつ病や軽度の認知症が進行すると、
片付けそのものが「負担」や「混乱のもと」として認識され、避けられるようになります。
こうした背景を知らずに、単に
「なんでこんなに汚いの?」
と責めてしまうと、
親との関係性がこじれるだけでなく
片付けはより進まなくなってしまいます。

「親の心を尊重すること」
片付けは「親の心を尊重すること」から始めよう
実家の片付けは、物を減らす作業であると同時に、親の人生と向き合う時間でもあります。
長年積み重ねてきた生活や思い出は、私たちが思う以上に深く根付いています。
だからこそ、ただ捨てるのではなく、「心を尊重する」ことが出発点になります。
いきなり捨てない・責めない
片付けの現場で最もやってはいけないのは、
親の了承を得ずに物を捨てることや、
「なんでこんな物を取ってあるの?」と責めることです。
本人にとっては、どんなに古びた紙袋や雑誌でも、
それは当時の思い出や、安心感を与える存在かもしれません。
特に、長年一人で暮らしてきた高齢者にとって、
物は“会話相手”や“家族の代わり”のような役割を持つこともあります。
そこに踏み込んでしまうと、信頼関係が崩れ、片付けが中断してしまう可能性があります。
「物」より「思い出」に寄り添う会話がカギ
片付けのゴールは、単に部屋を空っぽにすることではありません。
親が安心して暮らせる空間をつくることです。
そのためには、まず「何を残したいか」ではなく「どんな思い出を大切にしているか」を聞くことが大切です。
たとえば──
- 古いアルバムを手に取ったら、一緒にその時代の話を聞く
- 旅行土産や記念品なら、その背景や思い出を話題にする
こうした会話を重ねることで、「これはもう手放してもいいかもしれない」という気持ちが自然に生まれます。
結果として、捨てることが目的ではなく、
思い出を整理する過程の中で片付けが進むのです。
例えば、筆者のオススメは「古い写真」や「思い出の品」などをデジタルの写真で撮影、
思い出としてデータ保存で残しておく。
そうすれば、実物は処分でき、思い出は半永久的に保存できますので是非試してみてください。
ゴミ屋敷を防ぐ!高齢の親とできる片付けのコツを3つで紹介
① 一日5分の「見える場所」整理からスタート
片付けの習慣を身につけるには、いきなり家全体ではなく
玄関・ダイニングテーブル・リビングの一角など、目につく範囲から始めるのが効果的です。
一日5分だけでも「物が減った」という実感が親にも伝わり、
継続しやすくなります。
さらに、玄関やテーブルが整うと、湿気やホコリの溜まりにくい環境になり、
こもった臭いやカビ臭も軽減されます。
② 「使っていない物」より「使っている物」を聞く
「何を捨てるか」を基準にすると、捨てる理由探しになってしまいます。
そこで、まずは「今、よく使っている物はどれ?」と尋ねます。
よく使う物を基準に置き場所を決め、それ以外を別の場所に移すだけでも、
自然と不要品が浮かび上がります。
この方法なら、感情的な衝突を避けながら片付けが進みます。
また、使っていない物は湿気や埃を吸いやすく、長期間放置されることで
古紙や布のカビ臭、防虫剤のきつい臭いの発生源になります。
早めに処分することで、臭いの蓄積も防げます。
③ プロと一緒に“第3者視点”を入れるとスムーズ
どうしても進まない場合は、片付けや整理の専門業者を交えて作業するのも有効です。
家族だけでは感情が絡み、同じ場所で何度も作業が止まることがありますが、第三者が入ると会話の流れが変わり、スムーズに判断できるようになります。
特に、長年染みついた生活臭や収納奥のカビ臭などは、一般的な掃除では取り切れません。
プロは、消臭や除菌を並行して行えるため、衛生面でも安心です。
まとめ ── 実家を守ることは、親を思うこと
片付けは、ただ物を減らす作業ではありません。
そこには、親のこれまでの暮らしや思い出が詰まっており、手放すには勇気が必要です。
高齢の親との片付けは、物を捨てることよりも
「安心して暮らせる環境を一緒につくること」が目的です。
部屋が整えば、足元が安全になり、転倒や怪我のリスクも減ります。
空気の流れがよくなり、こもった臭いや湿気も少なくなります。
そして何より、親が笑顔で暮らせる空間は、家族みんなの心の安心にもつながります。
今日の小さな一歩が、未来の大きな安心に変わる──
そう信じて、片付けを始めてみてください。
片付けのご依頼ご相談は → 株式会社ラスティック